この記事は以下のような方にオススメです。
- 昇進や転職に向けて新しいスキルを身につける必要がある方
⇒リカレント教育の力強い味方となるJMOOCを紹介しています。 - 何かしら新しいことにチャレンジしてみたい方
⇒手軽に始められる学びの場としてのJMOOCを紹介しています。 - JMOOCの概要について気になっている方
⇒受講可能なプラットフォームや講座の特長について説明しています。
どうもこんにちは、じょんです。
先日読んだコチラの本。
本書の中では、人生100年時代において、私たちが長く生計を立てるためには、人生の各段階において継続的に新しいスキルを身につけていく、いわゆる『リカレント教育』の必要性が説かれています。
リカレント教育というのは、一言でいえば『学びなおし』を意味し、一度社会に出た後に、自身のキャリアを考える中で改めて学びなおす必要があると判断した領域について学習することを指します。
そして、このリカレント教育を行う上で、私たちにとって非常に心強い味方になりえる存在、『JMOOC』について今回は解説をしていきます。
JMOOCの概要
MOOCとは何か?
まずは『JMOOC(じぇいむーく)』の定義について、頭の『J』はJapanを意味しており、日本版の『MOOC(むーく)』のことを『JMOOC』と呼ぶわけですが、『MOOC』というのは、Massive Open Online Courseの略で、日本語では『大規模公開オンライン口座』と訳します。
これだけではイメージがつきづらいかも知れませんが、皆さんもYoutube等の動画配信サービスで何かを学ぶことありませんか?
正しくそれがMOOCのイメージであり、MOOCと呼ばれるものは、該当のオンライン講座が大学を含む学術機関や企業から体系的に提供されるものを指すことが一般的です。
MOOCのメリット
MOOCのメリットとしては以下の4点が挙げられます。
誰でも受講できる
MOOCには一般の大学のように入学試験などはなく、受講したい人間は誰でも登録をするだけで受講することが可能です。
また、多くの口座は無料で受講することができるため、PCやスマホ等のデバイスと、インターネット環境さえ揃っていれば、お金の面からも誰でも受講ができるといえます。
いつでも受講できる
MOOCは、一般の大学の授業のように決められた時間にしか講義が開催されないわけではなく、受講者は好きな時間に講義を視聴することができます。
既に社会にでている方が大学はビジネス大学院に通う場合には、通常は夜間に時間を作って通学するケースが多いですが、MOOCであればちょっとしたすきま時間にも受講が可能となるため、忙しい方にとっては非常に大きなメリットとなります。
どこでも受講できる
いつでも受講できる点とも少し重なりますが、受講者は視聴環境さえ揃っていれば、受講する場所を限定されません。
海外の講義を日本で受講することも可能で、物理的な距離による制約を受けない点も大きなメリットといえます。
幅広い講義を受講できる
一度講義の一覧をご覧になるとわかりますが、受講可能な講義は非常に多岐にわたっており、JMOOCであれば大学の講義と同様の数学や物理学から、SGDsやAIなどの比較的新しい分野、そして、金融リテラシーといった様々なテーマの講座を受講することができます。
また、海外のMOOCであれば、GoogleやFacobookといった超一流企業により提供されているものや、スタンフォードやハーバード、MITなどの超一流大学による講座なども受講可能となっています。
MOOCのデメリット
次にMOOCのデメリットとしては以下の2点が考えられます。
手軽であるがゆえに学ぶには強い意志が必要
誰でもいつでもどこでも受講できるメリットがある反面、特に無料で受講できる点から、受講者側の学びに対する意識が高くないと、自発的に取り組み続けることが比較的難しいという弊害が考えられます。
修了したことによる達成感が得にくい
こちらも手軽さゆえのデメリットと言えますが、少なくとも筆者の知る限りでは、JMOOCの講座を修了した際に、ちょっとした電子の修了証が発行されることがあっても、昇進や転職の場面で有利に働くということは想定されず、あくまで自己学習の範囲を超えないため達成感が得にくい点が挙げられます。
筆者もSGDsに関する講義を一通り受けたことがあるのですが、SGDsに関する理解が深まった点は良かったと思える半面、修了したことによる達成感を得ることは出来ませんでした。
あくまで実学として、学んだ事が直接現在もしくは将来の仕事に繋がることで達成感を高めることができるのだと筆者は感じました。
JMOOCの仕組みと講座内容
JMOOCプラットフォームの仕組み
さて、日本版MOOCたるJMOOCですが、日本オープンオンライン教育推進協議会により運営される『JMOOC』というプラットフォームが存在し、その中に『gacco』、『Open Learning』、『JMOOC PlatJaM』、『OUJ MOOC』という4つのサブプラットフォームが連なっているというイメージで成り立っています。
以下はJMOOCのWEBサイトへのリンクですが、下にスクロールしていただくと多くの講座が受講可能となっているのがわかり、それぞれの講座にサブプラットフォームのマークが付されているのが見て取れます。

私たち受講者は受講したい講座を選択すると、それぞれのサブプラットフォームに飛ばされますので、サブプラットフォームでアカウントを作成することで講座が受講可能となるという仕組みです。
ちなみに、JMOOCの講座が基本無料で受講できる背景には、各大学や企業がJMOOCへの講座の提供を通じて受講者のブランドイメージを高めることで、間接的にマネタイズができる点があると考えられます。
なお、海外のMOOCではマネタイズの手法も様々であり、基本無料としながらも、受講後の企業への就職支援や、有料会員向けの高度に専門的な講座を開設するなどの対応を進めているようです。
さて少し話がそれましたが、以降は、それぞれのサブプラットフォームについて簡単に概要を説明していきますが、『OUJ MOOC』については現在受講可能な講座がなく、今回は説明を割愛します。
gacco
まずは、NTTドコモの子会社であるドコモgacco社が運営する『gacco』です。

筆者の感覚からすると、幅広い受講者を対象としたライトな講座が多く開設されている印象であり、MOOCに初めて触れる方にとっては、親しみやすいプラットフォームとなっています。
現在公開されている講座でいうと、お笑い芸人の厚切りジェイソンさんによるマネーリテラシーの講座や、Googleによる働き方改革の講座、立命館大学によるSGDs関連の講座等、種類も豊富となっています。
Open Learning
次に、ネットラーニング社が運営する『Open Learning』です。
Open Learningの特長としては、海外の有名大学による講義が日本語の字幕付きで受講できる点にあり、現在受講可能な講座では、MITのビジネスプラン入門や、イェールの心理学入門など、MOOCの『どこでも受講できる』というメリットを上手く活かした講座が開設されています。
JMOOC PlatJaM
最後に、JMOOC自身が運営する『JMOOC PlatJaM』です。
正直、先に挙げたプラットフォームと比べて味気ない印象を受けますが、講座自体は国内の有名大学による講座を揃えており、大学で学ぶ内容を改めて学習したいという方にとっては向いていると言えるのではないでしょうか。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回とりあげたJMOOCですが、まだまだMOOC自体、日本では始まったばかりという印象であり、海外のMOOCに比べると講座の質・量ともに圧倒的に劣っているという印象を筆者は受けました。
例えば、海外のMOOCでの有名どころですと、CourseraやUdacityは世界中で多くの受講者が日々学んでいますし、Udemyは先日NASDAQに上場したばかりと、EdTechの一環として正に世界中が注目してる領域であるのは間違いないでしょうから、ぜひ日本でもMOOCが活発になることを切に願っています。
それではまた。


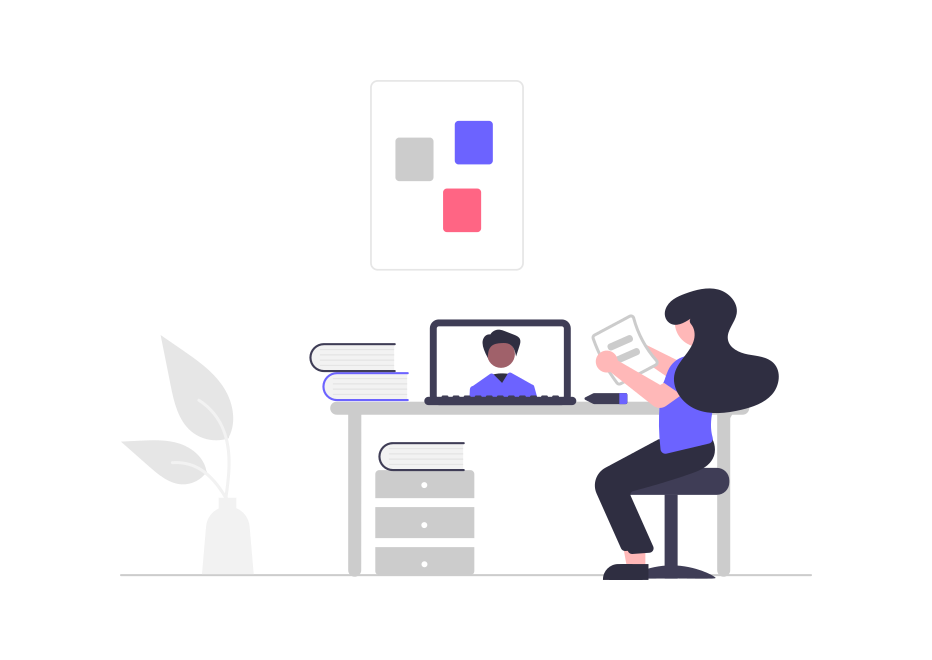
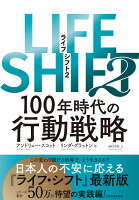


コメント